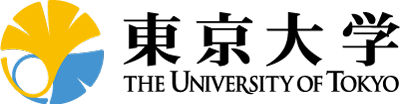国際総合日本学ネットワーク新プロジェクト「東京学派の研究」第1回ワークショップ
「アジアの概念化」
| 日時: | 2018年6月15日(金) 14:00~18:00 |
|---|---|
| 会場: | 東京大学東洋文化研究所 大会議室(3階) |
| 使用言語: | 日本語 |

概要:「東京学派」研究は、近代日本において、東京大学を中心として形成された学術が、いかなる問題系を構成し、それがどのような思想的、政治的、社会的な影響を与えたのかを、国際的な角度から総合的に研究し、新たな研究プラットフォームを作り上げることを目指す。東京大学は1877年の創設以来、欧州で育まれた学術のグローバル化の先陣を切り、現代に至るまでアジアにおけるその中心地となってきた。西田幾多郎らに代表される京都学派に対し、脱中心化されてきた東京学派の影響はかなり複雑な仕方で日本社会全体の構造に浸潤しており、このことが、同学派の批判的考察を困難にしてきた。しかしグローバル化がさらに進展するにつれ、同学派の実態をあきらかにし、近代日本学術の経験を国際的に共有する必要性が高まっている。本研究では、人文社会科学を中心に、東京学派という発見的な概念から、近代日本学術の経験を明らかにしたい。
東京大学を中心として東京に形成された学知(「東京学派」)にとって、アジアをどう概念化するかは喫緊の課題であった。それは、西洋近代の学知の対象であったアジアの一部である日本が、アジアをそして日本をどう位置づけるかという、複雑な構造において問われたものであった。第一回ワークショップでは、歴史家の石母田正と京城帝国大学の初代学長であった服部宇之吉を通し、東京大学を中心とした学知の形成と流通においてアジアがどのように言説化されたかを検討する。
発表者とタイトル:
磯前順一・国際日本文化研究センター教授
「内在化する『アジア』という眼差し: アジア的生産様式論争と石母田正」
本報告は、マルクスに端を発する「アジア的生産様式」をめぐる議論が、日本でどのように展開されていったかを追跡することにある。方法論的考察の鍵をなすのは、ポストコロニアル批評家エドワード・サイードの「オリエンタリズム」である。サイードはイスラムのイメージが、それを語ってきた西洋側の社会・政治的文脈のなかで決定されてきたことを明らかにした。その中で、野蛮なイスラムあるいは神秘的なイスラムという像が描き出されてきたのである。その視点からすれば、マルクス主義によるアジア論、具体的には「アジア的生産様式」の議論もまた、西欧人であるマルクスによるオリエンタリズム的な眼差しの中で、西欧人による他者像の表出の問題として提出されたものであることは確かである。
その議論は大きく分けて三段階からなる。一つ目は、マルクス自身の著作の中でのアジア像の変化。二つ目は、スターリン時代の、1920年代のソ連における中国の革命戦略を通した、アジア的生産様式をめぐる議論の政治的急進化とその挫折。そして、三つ目の1930年代から本格化する、日本のマルクス主義歴史学におけるアジア的生産様式論の議論である。言うまでもなく、本報告では、この三番目の段階に焦点をおいて議論を整理していく。第三段階の日本マルクス主義の議論が本報告の中心となる。議論はマルクスの草稿『資本主義制生産をめぐる諸形態』の前と後とでまず二期に分かれる。すなわち、戦前の議論と戦後の議論である。前半の議論の中心が羽仁五郎や平野義太郎ら、『資本主義発達史講座』の寄稿者である。そこではアジア停滞論が中心の議題となり、1933年の共産党員の大量転向を契機として、大東亜共栄圏を正当化する議論へとアジア的生産様式論は転用されていく。後半の議論はマルクス主義における世界史の基本法則を前提として、「アジア的生産様式論」が基本法則の一段階なのか、地域的多様性の一変種なのかという主題へと展開されていく。その時代の牽引者となったのが松本新八郎や石母田正であった。ただし、かれらはアジア停滞論には一定の距離を置いており、アジア的生産様式論という名前を表立って使うことはなかった。
しかし、とくに石母田は『諸形態』の「総体的奴隷制」という議論に着目し、在地領主制から在地首長制へと議論を、1945年から1970年代にかけて展開していく。そのなかで完成したのが二次的生産関係としての古代国家論、すなわち『日本の古代国家』の議論であった。こうした議論は、東大法学部の平野義太郎・羽仁五郎、東大文学部国史の松本新八郎・石母田正、そして経済学部の安良城盛昭と、一貫して東大出身の学者が関与してきた。彼らが『日本歴史教程』の領袖である渡部義通、京都大学の原秀三郎らと激しい討論を重ねてきた中で、アジア人によるアジア認識として「アジア的生産様式」をめぐる議論は一定の成果を収めてきたのである。見方によっては、西欧人によって外在的に規定された「アジア」というイメージが、ロシア人の議論を介して、日本人による自己認識として内在化されたといってよいであろう。
だとすれば、本報告の主題は、その内在化過程によって、アジア人による自己認識に何がもたらされたのかを明らかにすることにある。それはサイードが言うように、外圧的なオリエンタリズム的視点を内在する過程によって、その認識にどのような変化がもたらされるか。サイードの段階には明らかではなかった、外部の眼差しと内部の眼差しの交錯過程における新たな認識の生成という視点を、日本のアジア的生産様式をめぐる議論から提示することになるだろう。その軸に東京学派が存在したことは明白である。
松田利彦・国際日本文化研究センター教授
「植民地朝鮮における東京帝国大学の学知―服部宇之吉と京城帝国大学の創設をめぐって」
戦前の「東京学派」の問題を考える際、日本「内地」と植民地を横断する帝国史的観点を欠かすことはできないだろう。台湾・朝鮮総督府に送りこまれた植民地官僚、京城帝国大学(1926年学部開設)および台北帝国大学(1928年開学)において生みだされた学知、あるいは植民地から「内地」への台湾人・朝鮮人留学生―こうした問題のいずれをとっても、東京帝国大学が帝国日本に及ぼした影響は大きい。
本報告は、服部宇之吉(1867~1939年)について、京城帝国大学(1924年予科開設、26年学部開設)創設者としての側面から検討する。服部は、戦前日本における「東洋学」の創始者の一人として、あるいは中国における教育事業への関与によって知られるが、京城帝大初代総長としての経歴についてはほとんど研究がなされていない。たしかに服部が京城帝大総長をつとめたのはわずかに一年余にすぎない(1926年5月~27年7月)。服部自身の記した「服部先生自叙」(服部先生古稀祝賀記念論文集刊行会編『服部先生古稀祝賀記念論文集』冨山房、1936年)においても、京城帝大の創設に関する記述はわずか数行に過ぎない。
しかし、個人の行った事業が、本人の意図を超えて歴史上に大きな位置を占めることは決して珍しいことではなかろう。服部のつくった京城帝大も、今日、「親日派」を生みだす「植民地支配の装置」として指弾され、ひいては解放後韓国に引き継がれる学歴ヒエラルキーの淵源(丁仙伊)という批判まで受けている。資料的裏付けを必ずしもともなわないまま、評価が先行している感もある服部と京城帝国大学創設の関係について、朝鮮総督府の大学設立構想の文脈を踏まえながら検討したい。
討論者: 園田茂人・東京大学東洋文化研究所教授、中島隆博・東京大学東洋文化研究所教授
主催:科研費プロジェクト「東京学派」研究
共催:東京大学国際総合日本学ネットワーク(GJS)、東京大学東洋文化研究所(IASA)
問い合わせ:gjs[at]ioc.u-tokyo.ac.jp